ゴシック建築を賛美した二人
原書は1969年に出版された。著者のニコラウス・ペヴスナーは美術史家として多数の著作を持つ。ペヴスナーは1902年にドイツに生まれる。ユダヤ人だったペヴスナーはナチスの迫害を逃れるためにイギリスに渡り、そこで美術史家として活動する。
この本ではジョン・ラスキンとウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュクについて語っている。
ラスキンは19世紀のイギリスを代表する評論家。とくにゴシック建築を賛美した『建築の七燈』という建築書で有名な人物。ヴィオレ・ル・デュクはラスキンとほぼ同じ時代に活躍したフランスの建築家で、中世の建築を多数修復したことで知られる。ヴィオレ・ル・デュクはゴシック建築の構造を合理的に解釈し、これによってフランスでのゴシック建築に対する評価が高まった。
ラスキンは1819年生まれ、ヴィオレ・ル・デュクは1814年生まれ。二人にはイギリスとフランスという違いがあったが、同じ時代にゴシック建築を高く評価するという共通点があった。二人が活躍した時代、19世紀にはゴシック・リヴァイヴァルと呼ばれるゴシック建築の復興運動があった。フランスでのゴシック・リヴァイヴァルを牽引したのはヴィオレ・ル・デュクだった。

セント・フィン・バーレの大聖堂
(https://ja.wikipedia.org)
著述の人と実践の人
ペヴスナーは二人の違いについて次のように述べる。
「ラスキンは語る人であり著述の人であったのに対して、ヴィオレ・ル・デュクは実践家だった。」
ラスキンは評論家として美術や建築についての文章を残しているが、実際に建築物を残してはいない。一方、ヴィオレ・ル・デュクは中世の教会や城の修復というかたちで建築の実作を残している。ヴィオレ・ル・デュクは『フランス建築事典』『建築講話』の書籍を残してはいるが、数は多くない。
二人はともにゴシック主義者だった。しかし同じゴシック建築を見ていても、二人は全く異なる視点で見ていた。ラスキンの『建築の七燈』はタイトルが示すように、七つに分かれている。それらは「犠牲の燈」、「真実の燈」、「力の燈」、「美の燈」、「生命の燈」、「従順の燈」、「記憶の燈」の七つだ。ペヴスナーは「これらはすべて感情を喚起する特質ばかりではあるが、厳密にいえば建築的なものではない」と述べている。
ヴィオレ・ル・デュクの場合はどうか。
「それに対してヴィオレ・ル・デュクの『事典』の第二巻を開けば、そこには「祭壇」、「手摺り」、「柱基」、「大聖堂」、
「礼拝堂」、「柱頭」などの項目がならんでいる。」
この違いについてペヴスナーは「一方は感情の魔術師であり、他方は事実の報告者だという両者の対照がここに見られる」と述べている。
ラスキンはゴシック建築の素晴らしさを、その装飾を担った彫刻家たちによるものと考えている。それに対しヴィオレ・ル・デュクはゴシック建築の合理的な構造の論理を称え、その設計者たちを賛美する。
ラスキン「建築は彫刻」
ラスキンは、建築の質というものは、それを作った彫刻家の質によって決まると考えていた。重要なのは建築家ではなく、彫刻家なのだ。
ペヴスナーはラスキンの以下の文章を引用する。
「すべての装飾に対して発せられるべき正しい問いは、単純につぎのようなものである。すなわち、それは喜びをもってなされたか--彫刻職人はその装飾にかかっているとき幸せであったか、である。」
建築物の出来ではなく、その作業中の彫刻家の状態を問うべきだと言うのだ。ラスキンは設計者についてはほとんど語らない。その理由をペヴスナーは次のように解説する。
「なぜなら、建築を単なる建物から区別するものは、デザインの問題ではなく装飾の問題なのだというのが彼の信念だからである。」

ジョン・ラスキン
(https://en.wikipedia.org)
ラスキンの考えは、建築とは建物のうえに刻み込まれた「それ以外には何の必要もない、ある種の尊厳あるいは美の性格」というものなのだ。彫刻家が施す装飾は、「それ以外には何の必要もない」ものだとはっきりと言っている。しかしここには否定的な意味合いはない。むしろ必要ではないものを付加することに意味があり、このことではじめて価値が生まれる。必要なものだけで作られたものは単なる建物であって建築ではないというのがラスキンの信念なのだ。ラスキンは、彫刻と絵画こそ建築の主人だとする。
そしてラスキンは彫刻や絵画について、「自然界の事物を彫ったり描いたりしたもの」であるときにのみ高貴な芸術たりうる、と考えていた。自然には定規やコンパスで測ったようなものはない。均整が常にとれているわけではなく、粗さや不完全なものが多数ある。ラスキンは「不完全さのない建築は、真に高貴ではないありえない。」とする。
完全ではないということが進歩と変化の状態を表している。変化に富み、多様であることが、自然を表現しようとするときのあるべき姿なのだ。ラスキンは「高潔な建築くらい高慢な」建築はないと考える。
ラスキンは次のようにも書いている。
「もしひとつの部分がいつでも正確に他の部分に対応しているなら、それは明らかに悪い建物である」
「もし不規則性が大きければ大きい程、またこみいっていればいる程、それは良い建物である可能性が大きい」
ペヴスナーは、それに対し「しかしこれらはすべて感覚であり、理論ではない。」と断言する。
ヴィオレ・ル・デュク「建築は設計」
ヴィオレ・ル・デュクはラスキンとは異なる考えを持っていた。ゴシック建築で、偉大な大聖堂をつくり上げたのは、ラスキンによれば粗野な彫刻職人たちだったが、ヴィオレ・ル・デュクによればそれをつくったのは知的なデザイナーであった。なぜならゴシック建築は理性と科学にもとづいて合理的に設計されており、この合理主義こそがゴシック建築の特徴だと考えていたからだ。
この合理的に設計されたという理解は、ヴィオレ・ル・デュクが建物の修復作業をしていくなかで得られたものだった。
フランスにはエコール・デ・ボザールと呼ばれる建築の教育機関がある。建築のほかに絵画や彫刻を含む美術全体を扱う上部組織があり、さらにその上には美術、文芸、科学、政治などをまとめる組織があった。つまりフランスの学術分野全般がアカデミーと呼ばれるピラミッド型の組織によって構成されており、長い伝統と絶大な権威を持ったアカデミーが支配していた。
エコール・デ・ボザールでは毎年、ローマ賞という設計競技があり、受賞者は複数年ローマに留学することができた。そのローマで古代・古典の実地研究をおこない、レポートを提出するという課題があった。当時はヨーロッパの建築の起源は古代ローマにあるとされていた。
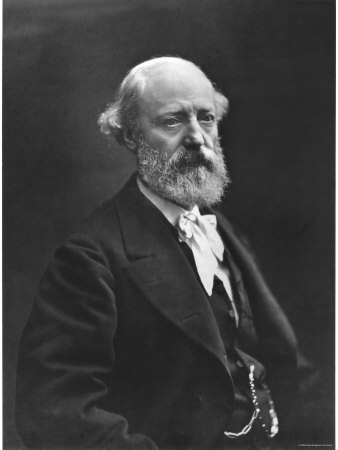
ヴィオレ・ル・デュク
(https://en.wikipedia.org)
ヴィオレ・ル・デュクはエコール・デ・ボザールでは学んでいない。アカデミーで正式な教育を受けずに建築の仕事に就いた。修復作業で建築の構造を学び、ゴシック建築の合理性に感銘を受けた。同時にフランスのアカデミーが古代ローマに傾倒し過ぎていると感じ、ゴシック建築こそがフランスならではの様式ではないかと考えるようになった。
ペヴスナーは次のように書く。
「そしてもうひとつの核心は--アカデミーの古典主義やイタリア主義に対抗するために常に用いられる--ゴシックはフランスの国民的様式であるという議論である。」
ヴィオレ・ル・デュクは当時の絶対的な権力を持ったアカデミーに対して挑戦的な態度をとりつづけ、『建築講話』で自らの建築理論を書き残した。
ヴィオレ・ル・デュクとモダニズム
本書でペヴスナーは、ヴィオレ・ル・デュクは合理主義的、ラスキンは感覚的という違いがあると示している。ペヴスナーはこれを「フランス性」と「英国性」という言葉で表している。
ラスキンの自然を愛し、それをあるがままに表現することが美であるという考えは、その後ウィリアム・モリスに受け継がれた。産業革命がおこり、廉価で粗悪な工業製品があふれ、人間らしさや自然が疎外されていくなかで、アーツ・アンド・クラフツ運動として装飾や工芸を見直す動きへと繋がった。
ヴィオレ・ル・デュクは、その後のモダニズムに見られる、合理主義的な視点で建築を見ていた。さらに鉄やガラスなどの新しい建築材料や、鉄道駅のような新しい建築の機能に対しても前向きに評価していた。
しかしヴィオレ・ル・デュクは新しい様式をつくれなかったと、ペヴスナーは指摘する。理論や考え方はモダニズムに近かったが、ヴィオレ・ル・デュクがつくった建築は前近代的なものだった。
ペヴスナーは「ヴィオレ・ル・デュクだけでなく、ピュージン、スコット、バージェスも」誰も新様式をつくれなかったと述べる。
ピュージンとはオーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージン、スコットはジョージ・ギルバート・スコット、バージェスはウィリアム・バージェス、それぞれ19世紀のゴシック・リヴァイヴァルを代表する建築家たちだ。

セント・パンクラス駅
(https://en.wikipedia.org)
なぜ彼らは新しい様式をつくれなかったのか。ペヴスナーは推論として次のように解説する。
19世紀絵画には進歩派と伝統派、新派と折衷派があった。進歩派や新派は「受け入れられざる者」であり、伝統派や折衷派は「受け入れられた者」だった。しかしこれらは絵画での話であり、建築には進歩派や新派にあたる「受け入れられない者」が存在しなかった。なぜなら、絵画は受け入れられなくても画家が一人で部屋に篭って製作できるが、建築では施主やパトロンといった「受け入れてくれる」存在が必要だからだ。ペヴスナーは「受け入れらるざる建築というのは、存在しようがない」と書く。
ヴィオレ・ル・デュクは新しい建築様式をつくることはできなかった。しかし彼の、建築を合理主義的にとらえる見方や、新しい素材を前向きに取り入れる姿勢は、のちの建築に大きな影響を与えた。